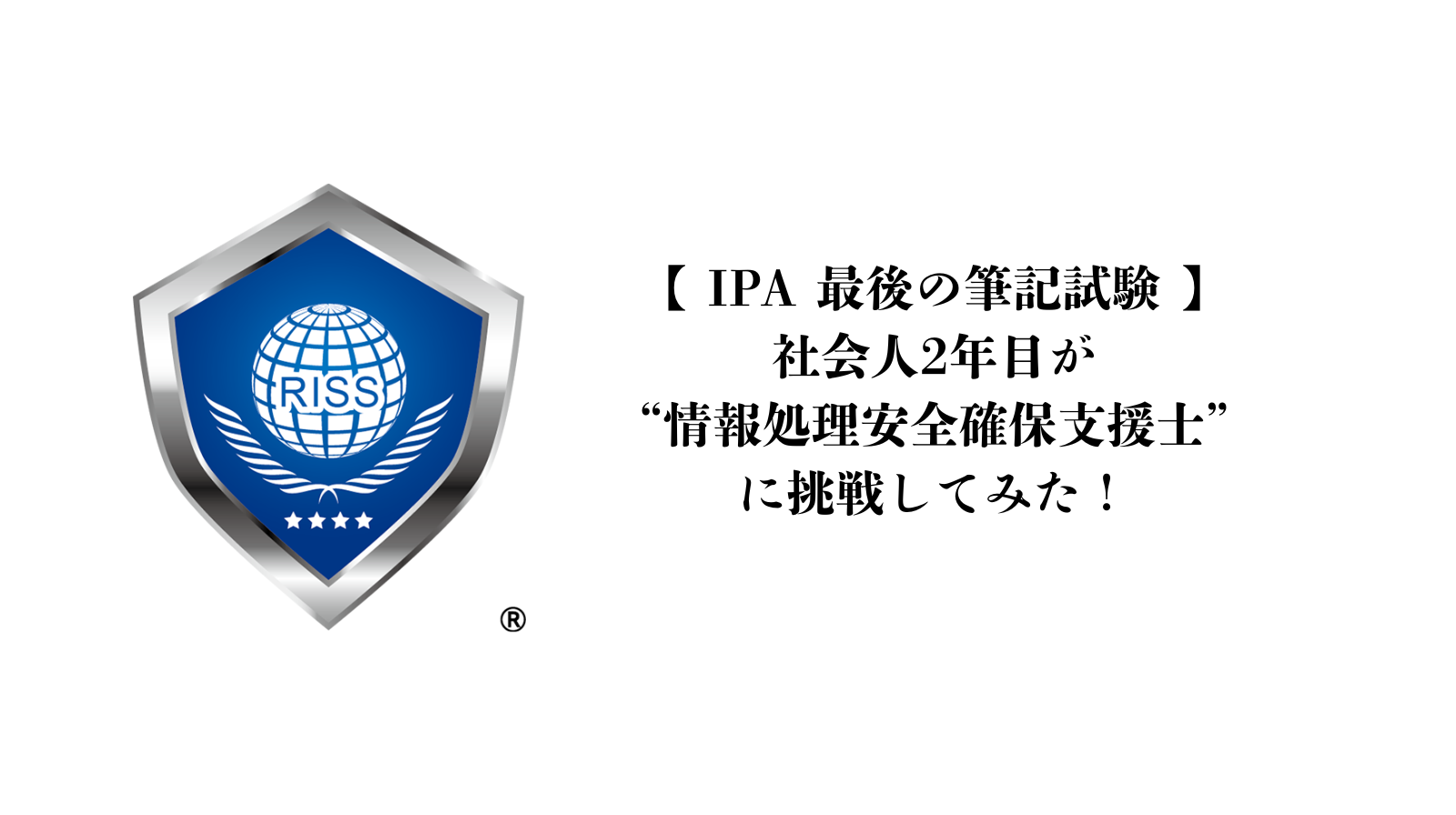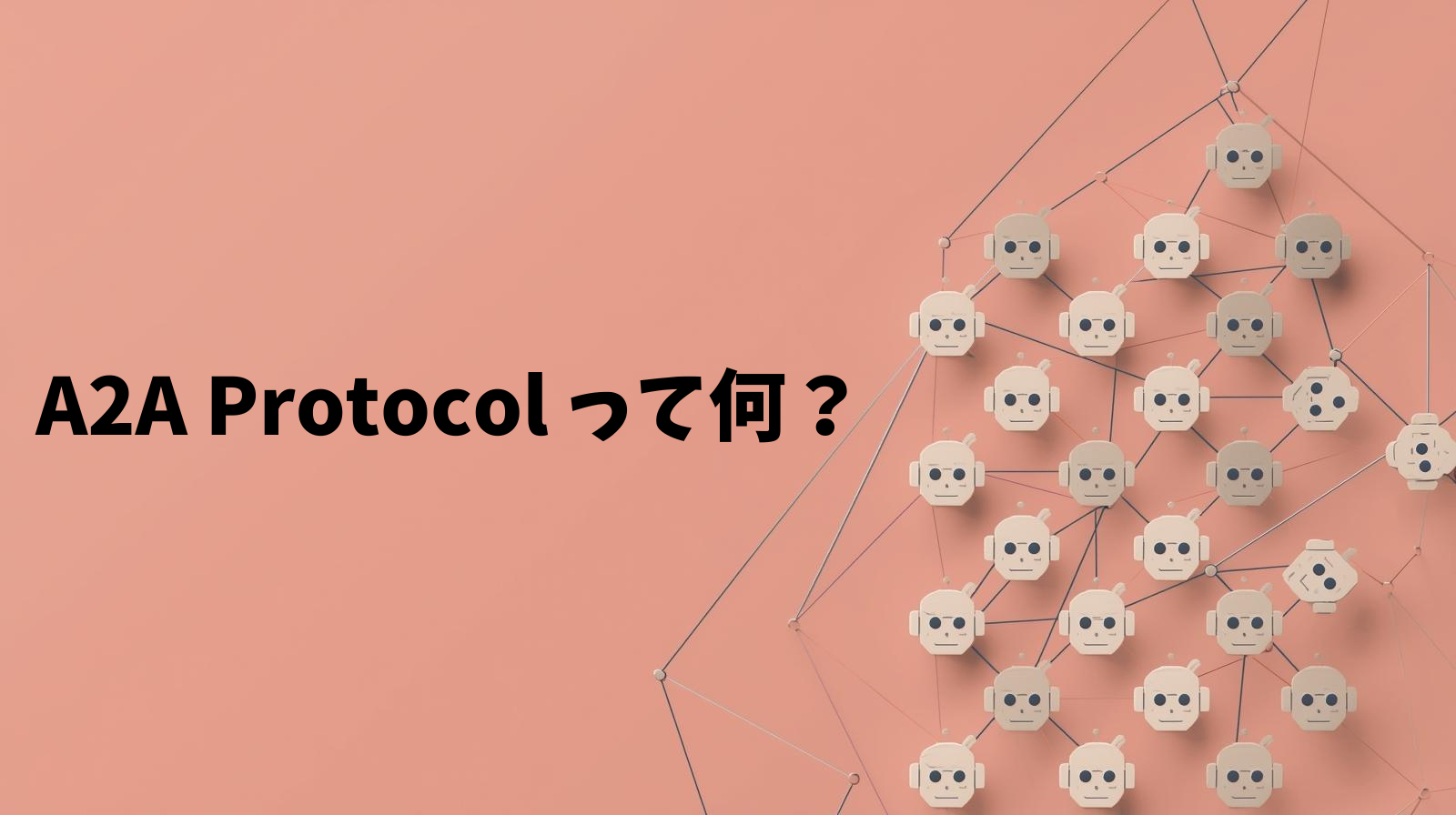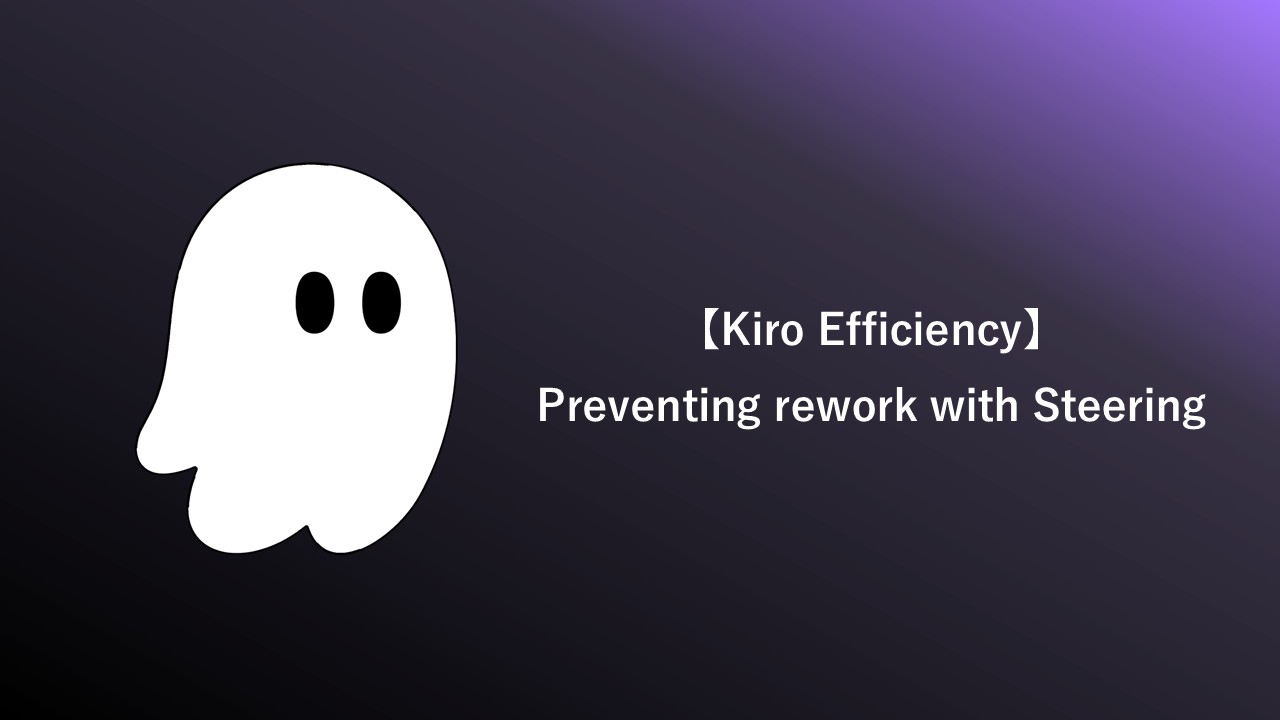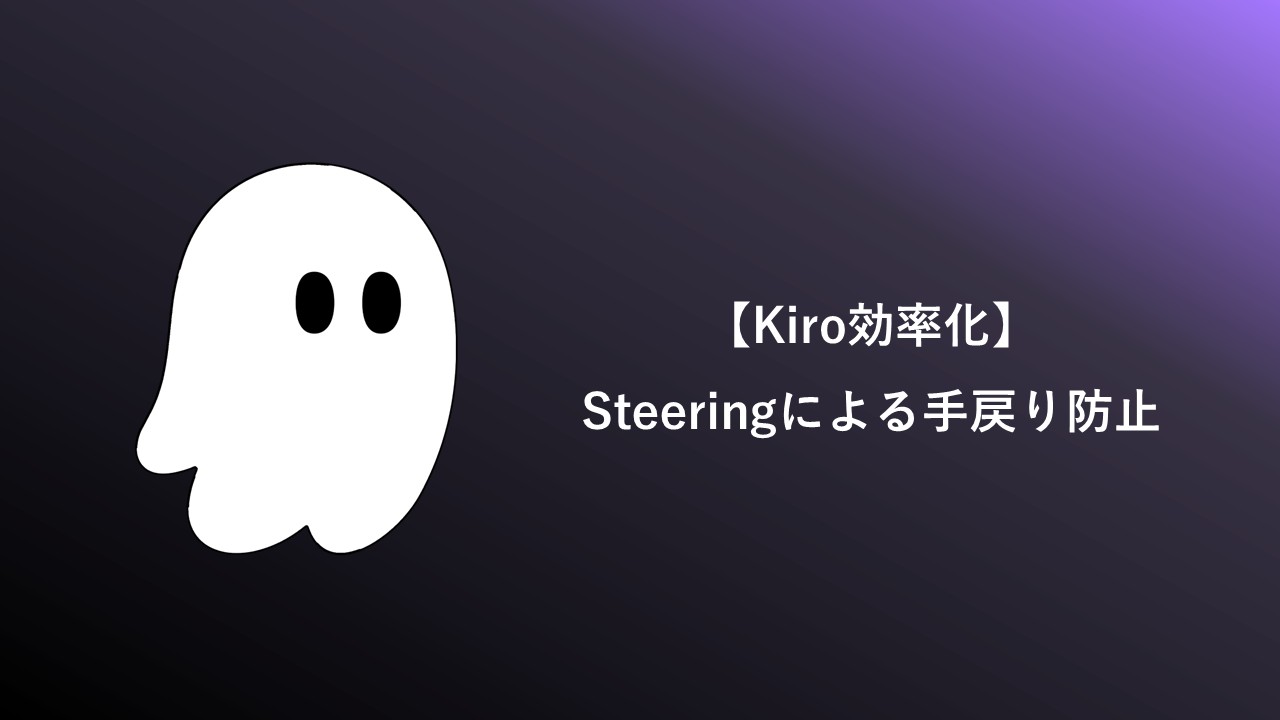記事公開日
【合格体験記】AI-900 & AI-102 ダブル受験してみた!
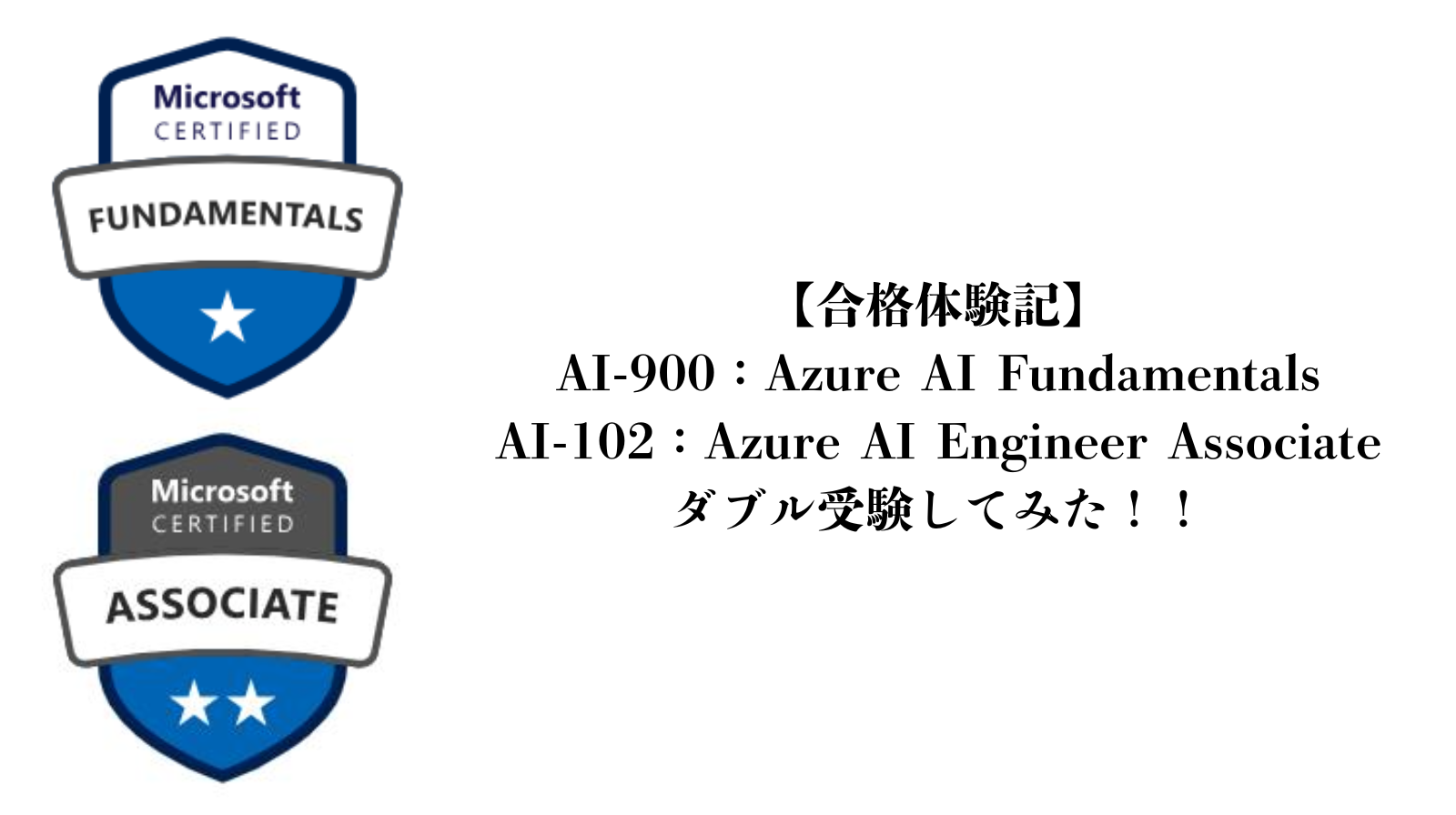
こんにちは!大和矢です。
先日、MicrosoftのAI資格である「AI-900:Azure AI Fundamentals」と、その上位資格にあたる「AI-102:Azure AI Engineer Associate」を1日のうちに連続で受験し、合格することができました。
本記事では、私が実践した勉強法、学習時間の内訳等をご紹介します。
これから挑戦するあなたの学習計画のヒントになれば嬉しいです。
筆者のスペック
初めに、筆者のスペックを簡単に記載します。
- 新卒QES入社2年目(24卒 / 社会人2年目)
- 非情報学部卒(IT未経験)
- Microsoft資格
入社1年目:「AZ-900」「PL-900」「MS-900」取得 - その他資格(IPA)
入社1年目7月 「基本情報技術者試験」取得
入社2年目4月 「応用情報技術者試験」取得(2025年春期試験)
入社2年目10月「情報処理安全確保支援士試験」受験(2025年秋期試験)
最近の業務では、Azure OpenAIを使った開発をしていますが、その他のAzure AIリソースについては、ほとんど触れてきませんでした。
受験のきっかけは、自分への「再点火」
実は、この2つの資格取得は、今年の初めに立てた目標でした。
「なぜ、2025年も終盤のこの時期に?」と思われるかもしれません。
正直に言うと、なかなか勉強のやる気に火がつかなかったです。
言い訳のようになってしまいますが、4月に「応用情報技術者試験」、10月に「情報処理安全確保支援士試験」と、今年はIPAの国家試験に集中していました。
筆者はマルチタスクが得意ではないので、IPAの試験勉強を理由にMicrosoftの試験勉強を後回しにしてしまいました。
実際は、IPAの勉強も2カ月前くらいからスタートしていたので、年中勉強していたわけではないんですけどね。
そんなわけで、10月12日、最後の山場だった情報処理安全確保支援士試験が終了。
燃え尽きてしまいそうな解放感と同時に、「ここで途切れたら、もう勉強しなくなるぞ」という危機感が湧いてきました。
せっかく熱くなった学習のモチベーションが冷めてしまう前に、その勢いを借りて、自分を次の目標へ突き動かすため、試験が終わった直後に「AI-900」と「AI-102」の予約ボタンをクリックしたのです。
「情報処理安全確保支援士試験」の受験体験記については、以下ブログで紹介しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。
AI-900とAI-102とは??
今回私が受験した「AI-900」と「AI-102」について、簡単にご紹介します。
どちらもMicrosoft AzureのAIに関する認定資格ですが、対象者と問われるスキルレベルが異なります。
AI-900:Azure AI Fundamentals
一言で言うと、「AzureのAIサービスで何ができるのかを幅広く知るための入門資格」です。
- 対象者:
- AIや機械学習の概念を学びたいと考えているすべての人
- 技術的な職種だけでなく、営業や企画職など、AIソリューションの価値を理解したいビジネスサイドの方 - 問われるスキル:
- 機械学習、コンピュータビジョン、自然言語処理(NLP)、生成AIといったAIの基本的な概念の理解
- Azure上で提供されている各AIサービスが、どのような課題を解決できるかの知識
- プログラミングやAzureの操作スキルは問われず、主に知識問題が中心
AIの世界への第一歩として、また、AzureでAI活用を検討する際の共通言語を身につけるのに適した試験と言えます。
AI-102:Azure AI Engineer Associate
こちらは、「実際にAzureのAIサービスを使って、ソリューションを設計・開発・実装する能力を証明するエンジニア向けの資格」です。
- 対象者:
- AzureのAIサービスを利用してアプリケーションを開発するAIエンジニアやソフトウェア開発者 - 問われるスキル:
- Azure AI Foundry、Azure OpenAI、Azure AI Visionなど、特定のAIサービスを実際に利用してソリューションを構築する具体的なスキル
- サービスのプロビジョニング、パフォーマンス監視といった、運用まで見据えた知識
- 一部の設問では、C#またはPythonのコードを読んで理解する能力も求められる
AI-900が「知っている」ことを証明する試験なら、AI-102は「(コードを書いて)実際に作れる」ことを証明する、より実践的な資格です。
学習方法
ここからは、私が実践した具体的な学習方法をご紹介します。
結論から言うと、AI-102(上位資格)の対策に集中し、AI-900(基礎資格)は勉強しませんでした。
約1週間、合計で8時間を確保しました。
| 学習時間(時間) | 学習方法 |
|---|---|
| 7 | Microsoft Learnを使用し、AI-102の学習パスに沿って、すべてのモジュールをざっと一周 「どのサービスで何ができるのか」という全体像を掴む |
| 1 | Microsoft Learnにある、AI-102のプラクティス評価を3周 |
AI-900を勉強しなかった理由としては、AI-102の学習範囲がAI-900の内容を包含していると思ったからです。
AI-102の学習を、AI-900の学習とみなしていました。
学習中の発見:進化し続けるAIの世界
余談ですが、「AIエージェント」や「MCP (Model Context Protocol)」、「A2A (Agent2Agent)」といった、比較的新しい概念や最新のサービスまでが学習パスに含まれていたのが興味深かったです。
AI-102の学習パスで「A2A」というプロトコルを初めて知り、勉強になったので、アウトプットとして技術ブログで公開しています。
試験結果:ギリギリの戦いを制す!
さて、気になる試験結果ですが…正直に告白します。なかなかにスリリングな結果となりました。
- AI-900 → 731点 (合格ライン: 700/1000点)
- AI-102 → 700点 (合格ライン: 700/1000点)
そうです、AI-102はなんと合格最低点ジャスト!
画面に「合格」の文字が見えた瞬間は、喜びよりも安堵のため息が漏れました。完全に勉強不足でしたね。
実際に受験して感じたギャップと反省点
私の学習方法には、いくつか見込み違いがありました。これから受験される方は、ぜひ参考にしてください。
評価プラクティスと本番問題は別物だった
Microsoft Learnの評価プラクティスを繰り返すのが私の学習の主軸でしたが、本番では評価プラクティスと似た問題はほとんど出題されませんでした。
特にAI-102では、思った以上にPythonのコードを読み解く問題が多く、面食らってしまいました。
AI-900は「基礎概念」の理解が問われる
AI-102の学習だけではカバーしきれない部分もありました。
AI-900では、機械学習のライフサイクルや自然言語処理のタスクといった、より基本的なAIの概念を問う問題が出題されました。
幸い、私はもともと漠然とした知識があったため対応できましたが、AI初学者の方は、AI-900の学習パスでこれらの基礎概念をしっかり押さえておくことをお勧めします。
試験中のMicrosoft Learnは「保険」にならない
AI-102は、試験中にMicrosoft Learnのドキュメントを閲覧できるのが大きな特徴です。
正直、「最悪、調べればなんとかなるだろう」と高を括っていました。
しかし、いざ本番で使おうとすると、検索機能に慣れておらず、焦りもあって有効な情報を時間内に見つけ出すことができませんでした。
結果的に、Microsoft Learnの助けを借りて解答できた問題は一問もありませんでした。
Pythonのコード問題は、コード全体の文脈と選択肢の英単語の意味から推測して解答しました。
英語の意味が分かれば、意外と何とかなるのかなというのが感想です。
試験範囲の最新トピックはあまり出題されなかった
学習中には「AIエージェント」や「MCP 」、「A2A」といった最新の概念が含まれていて興味深かったのですが、実際の試験ではMCPやA2Aに関する問題は出題されませんでした。
AIエージェントに関しても、Semantic Kernelについて少し触れられる程度でした。
最新技術へのキャッチアップも大事ですが、まずは中核となるサービスの理解を固めることが合格への近道のようです。
まとめ
筆者の「上位資格の勉強に集中する」という戦略は、結果的にギリギリで通用しました。
しかし、もしより安心して合格したいのであれば、特にAI-102は模擬試験などを活用して、本番形式の問題に慣れておくべきだったと痛感しています。
とはいえ、なんとか一発でダブル合格という目標を達成できて、良かったです!
次の資格取得メイン目標は、IPAの「ネットワークスペシャリスト」なので(情報処理安全確保支援士試験が合格していればの話ですが)、並行してAzureの資格も取得していけたらいいなと思います。
QUICK E-Solutionsでは、各AIサービスを利用したシステム導入のお手伝いをしております。
それ以外でも QESでは様々なアプリケーションの開発・導入を行っております。提供するサービス・ソリューションにつきましては こちら に掲載しております。
システム開発・構築でお困りの問題や弊社が提供するサービス・ソリューションにご興味を抱かれましたら、是非一度 お問い合わせ ください。
※このブログで参照されている、Microsoft、その他のマイクロソフト製品およびサービスは、米国およびその他の国におけるマイクロソフトの商標または登録商標です。
※その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。